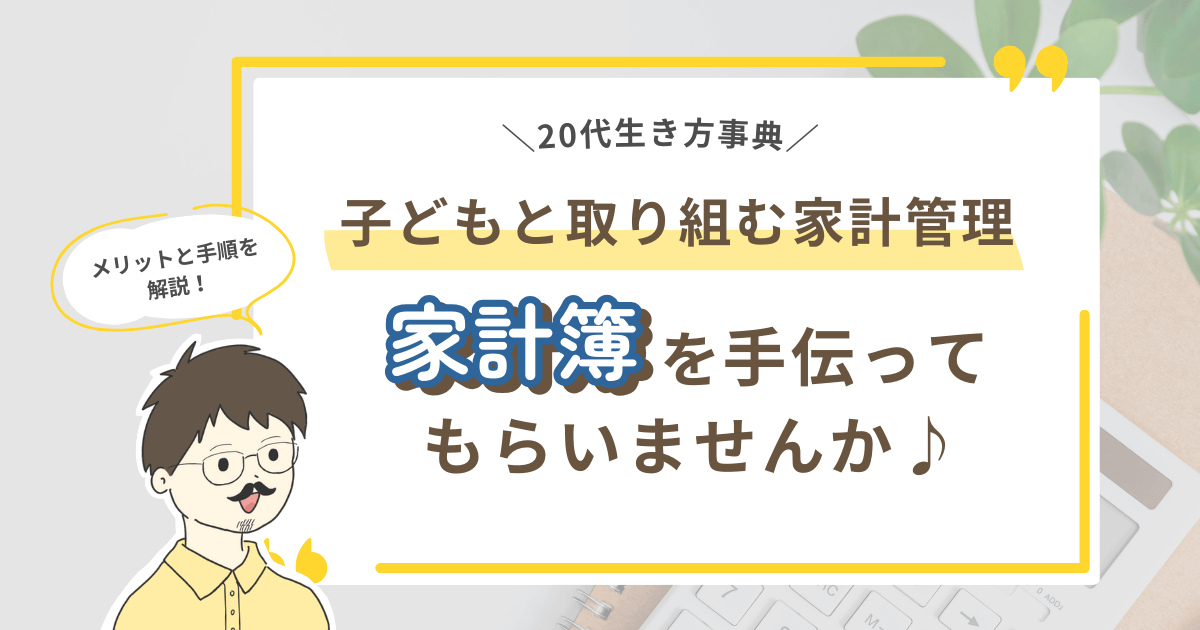今回は、ちょっと刺激的な提案をしたいと思います!笑
それは、、
家計簿を子どもに手伝ってもらいませんか??
これです!
 てつま
てつま刺激的でしょ?笑
というわけで、今日の本題は「家計簿を”家庭教育”に取り入れる」です!
賛否両論あるとは思いますが、長期的に見ればメリットのほうが大きくなるはず。
メリットや実例もお話ししていくので、参考にしていただければうれしいです!
ぜひ最後まで気楽に読んでみてください!



早いうちにリアルを知るべし…!
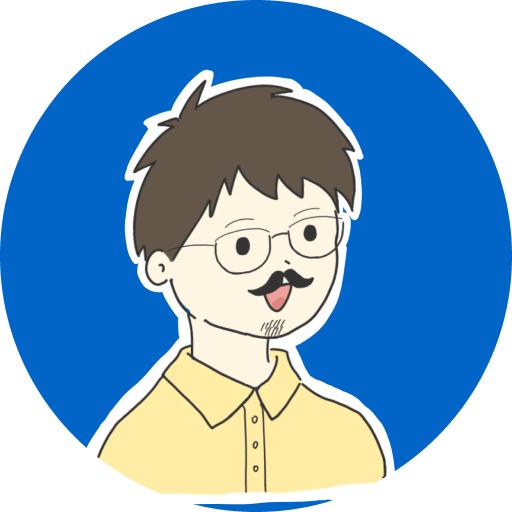
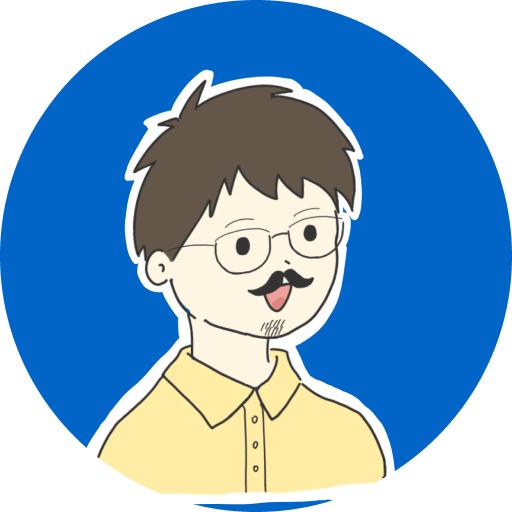
大学時代に「何のために生きていくのか」がわからなくなり、無気力な毎日を送る。
→24歳で、学校では習わない「人生のおもしろさ」を知り、衝撃を受ける!
人生でむっちゃ大事な、
- お金
- キャリア
- 人間関係
- 人生
に関する「人生の楽しさを家庭教育に」すべく、今日も発信します!
【家庭教育のカリキュラム】子どもに家計簿を手伝ってもらおう!
以前書いたこちらの記事で「家庭教育のカリキュラム」というものを提案させてもらいました!





下記の表です!
| 学年 | 「お金」 | 「キャリア」 | 「人間関係」 |
|---|---|---|---|
| 小4 | お金を敵視しない | キャリア・将来は 自分で作っていくと知る | 自分を大切にする |
| 小5 | 家庭内起業 | 家庭内起業 | 家族で横の関係を作る |
| 小6 | 家計簿を手伝う | 「仕事」「稼ぐ」の本質を知る | 「全員と仲良くする必要はない」と知る |
| 中1 | 何にお金を使うと幸せか、振り返る | 自己分析・自己理解をする | 自己理解 →価値観の合う仲間を把握し、大切にする |
| 中2 | 家庭内プレゼンをする | 人生の目的地を仮決めする | 横の関係を友達に広げる |
| 中3 | 未成年口座を作成する →少額投資 | 親の仕事・事業をサポートする | 家族、友達を無条件に信頼する |
| 高1 | 「お金に関する5つの力」を知る | 人生の目的地までの道のりをイメージ | 感謝する |
| 高2 | 自己投資をしてみる | 小さく起業する | 親切をする |
| 高3 | 「ほしい」を我慢する | 「やらないこと」を決める | 誘いを断る |
| 大1 | 自分に合った投資を実践 | 事業・副業にチャレンジ | 自分の得意なことで他人に貢献する |
| 大2 | 銀行口座・証券口座・クレジットカードを自分なりに最適化する | 自分の得意・苦手を把握 →苦手を減らし、得意に集中する | 人間関係を整理する |
| 大3 | こんまりメソッドを実践 | 事業・副業を軌道修正、再チャレンジ | 自分から関係を深めていく |
「お金」の項目、上から3番目に「家計簿を手伝う」を設定しています。
順番や年齢はあくまで目安ですが、家計簿を共有する機会を早めに設けてほしいなと思っています。
ここで、、



そんなことしていいのかな…。
と思われる方もいるかもしれません。



わかります、なんとなく不安ですよね。
そこで、参考になるいい記事を見つけたので、ご紹介させてもらえればと思います!
【実例】こんな記事を見つけました!
以下の記事、とてもおもしろくて参考になりました!


ざっくり内容をまとめると、、
- 大人になったときに、自分がお金に対して無知だったのを痛感した筆者
- 子どもには知っておいてほしい、という想いから、家計簿を子どもに見せることに。
- 毎月、収入・支出・投資をすべて共有
- 「お金の流れがわかる」「家計を考えられる」などのメリットあり
こんな感じです(楽しく読めるので、ぜひ見てみてください!)。
ほかにも調べてみると、子どもと共有している人は意外といらっしゃるみたいです。
また、日本よりも金融教育が進んでいるといわれるアメリカでは、家計簿を家族で共有するアプリなども充実しているらしい。。
というわけで、、



恐れることはありません!笑
先ほど紹介した記事では、家計簿を共有する前に、
「トップシークレットだから、言わないでね。」と子どもに伝えたそうです。
なんともほほえましくてユーモアのある伝え方ですよね。笑
「約束したところで、だれかに言ってしまうかもしれない。」と思われるかもしれませんが、そこはお子さんを信じてあげましょう。
そもそも家族内で信頼がなければ、何を教えることもできません。



家庭教育が成り立たなくなってしまいます。
お子さんを信頼し、ありのままを開示して、お子さんの成長に繋げていくことを優先しましょう!
家計簿を手伝ってもらうメリット・デメリット
先ほどの記事では「家計簿を共有する」という例でしたが、もう一歩踏み込んで「手伝ってもらう」を提案したいです!
もちろん、子どもが嫌がっていたり、つまんなそうであれば、そこまでする必要はありません。
でも興味を持ってくれたら、お子さんを「わが家の財務大臣」に任命し、手伝ってもらうとより大きな効果があるはず…!
そして、家計簿を手伝ってくれるなんて、立派な「仕事」ですよね。
なので、報酬を用意するのもぜひ検討してほしいと思います!
さらにその報酬が、家計簿にも反映されることで、よりお金の流れがわかるんじゃないかな、と。
それだけでも、かなりメリットは大きいと思っています。
「お金の流れの理解」以外にもメリットが大きいと思っていますが、逆にデメリットもあります。
というわけで、メリット・デメリットみていきたいと思います!



さっそくみていきましょう!
「家計簿を手伝う」のメリット
まずはメリットから。
今回は、大きなメリットを4つ挙げました!



サクッと4つみていきましょう!
1. お金の流れや相場が身に付く



これはもう言わずもがな、ですよね。
家計簿の中身を見ることで、子どものときにはなかなか知れないリアルを知ることができます。
代表的なものが税金。
子どものときに学校で習いますが、「消費税」くらいしか身近なものがなく、よくわからなかった記憶ないですか??
僕は、大人になって給与明細をみた時に、「本物の所得税だ!」って思いました。笑
そう、子どもにとって所得税・住民税は、名前は知ってるけど見たことのない、カッパやドラゴンのような存在なのです…!
ほかにも、家賃や水道光熱費など、大人になるまで知らずに生きることも少なくありません。
もちろんそうなると、金額の相場を知ることもありませんよね。



僕もそうでした!
いつかは知ることになるのなら、子どものうちにリアルな金額を知っておいていいと思います。
幻想を見せる必要性がわかりません。
将来どんなお金をもらったり、払ったりするのか、それぞれの相場がどれくらいなのか、を知ることができるのは一番のメリットといえますね!
2. 家計管理の経験・スキルが身に付く
お次は「手伝ってもらう」ことのメリット。
家計管理は、お金と健全に付き合ううえでとっても重要なスキル。
健康な体を維持するには、毎日体重計に乗ることが重要なように、
健全な財布を維持するには、家計をしっかり把握しておくことが大切です。
家庭でやってきたことは、大人になっても続けることが多いですよね。



歯磨きとかもそうです!
家計を把握するクセは、家計を把握することでしか身につきません。
家計簿を手伝ってもらうことで、「家計管理が大事」という感覚と「家計管理」という選択肢を持てるといいかなと思います!
3. 家族みんなで家計を改善する形になる
お子さんを「わが家の財務大臣」に任命することで、親が子どもに怒られることも出てくるのではないかと思っています。笑
子どものお金のムダ遣いは、親が止めますが、親のムダ遣いはいったい誰が止めてくれるのでしょうか?笑
家計簿をつけるのも親、財布を握っているのも親の場合、子どもにしか監視の目が届きません。
当然、親が何をやってもバレない、ということになってしまいます。
いっぽう家計簿を子ども、財布を握るのが親であれば、お互いに見張る形が生まれます。
そうなれば、家族みんなでよりよい家計を作っていけるはず。
ここまで意識が高まるかはわかりませんが、親子の上下関係はなくなり、チームとして動ける可能性もありますよね。
ぜひ、家族みんなで家計改善をしていく形を作っていきましょう!
4. 親が楽になる(笑)
家計管理をまかせることで、親の負担が減ります。笑



これは単純明快ですね!
計算が得意だったり、家計管理が得意だったりする子どもがいれば、喜んでやってくれるはず。
そしてきっと厳しく管理してくれて、家族全員のサイフの紐がかたくなることも期待できますね。笑
得意な人に、得意な仕事を任せるのはとってもいいことです。
単純な計算ができれば、家計簿の入力はできるので、小学生でも慣れればカンタンにできると思います。
楽になったうえに、教育にもなって、さらに子どもが楽しそうにやっているならこんなにいいことはありません!
積極的にお願いしてみましょう!



でも1つ注意点があります。
子どもが飽きてしまったときは、すぐに代わってあげましょう。笑
「家計簿を手伝う」のデメリット
デメリットのほうは、箇条書きで挙げていきたいと思います!
- 他人に流出する恐れがある
- 最初は教える時間がかかる
- 飽きてしまう可能性がある
1番のデメリットは先ほども挙げた通り、流出の危険性ですね。
ここに関してはもう正直どうしようもないと思います。笑
子どもを信頼しましょう!
1番やめていただきたいのは「脅す」こと。



「脅す」は信頼からもっとも遠い行為です。
信頼して共有し「誰かに話してしまうと、親が悲しい気持ちになるからやめてほしい。」ということだけ伝えておきましょう。
あとのデメリットも仕方がないところがあると思います。
最初は何をするにしても時間がかかるものだし、誰だって飽きることはありますよね。
でもこれらのデメリット以上にメリットが大きいと思っています。
最終的に飽きてしまったとしても、経験としては一生残りますよね。
大人になったときに「そういえば…」みたいな感じで思い出してくれるだけでも万々歳。
デメリットもありますが、なかなか代わりのきかないメリットがたくさんあるので、ぜひ取り入れてみてください!
「家計簿を手伝う」までの3ステップ
最後に「家計簿を手伝う」までの3ステップを紹介します!
それではそれぞれのステップを詳しくみていきましょう!
家計簿をつける
まずは当たり前ですが、家計簿をつけましょう!
家計簿にも種類が色々あるし、つけ方も人それぞれですが「自分のなかでしっかりルールが確立されていること」は必須です。



特に支出の管理ですね!
支出のほうが種類が多く、細かい分類になります。
管理法を改善して、大きな漏れのない家計簿ができたらOKです!
以下の動画などを参考にしつつ、自分なりの家計管理術を作りながら、家計簿をつけていきましょう!
また家計簿には、「マネーフォワードME」というアプリが便利です。
このアプリを使って、現金を使うのを避ければ支出管理はほとんど完璧になると思います。



できるだけ楽な方法を探してみましょう!
子どもに家計簿を共有する
ある程度、管理法が固まってきたら、家計簿を子どもに共有しましょう!
“ある程度”といったように、ほんとは完璧にするのがベストですが、まぁ大体がわかればいいと思います。
共有する一番の目的は、子どもに「お金の流れと相場を掴んでもらう」なので、少しの抜け漏れがあっても、目的は達成です!
できる範囲で精度を高めつつ、お子さんに見せてあげましょう。
冒頭で紹介した通り、共有するだけでもかなりのメリットがあると思います。
初めて目にするものに対して、素直な疑問や質問をいってもらい、話題にするのも◎ですね!
親が答えられないことが出てきても、一緒に学べば大丈夫!
親だって「知らないことはその都度学んでいる」という姿勢を見せることが重要です。
お金に関して、臆することなく話が飛び交う家庭作りを目指しましょう!
子どもに家計簿のつけ方を共有する
さてここまできたら、最後に家計簿のつけ方を共有し、子どもに手伝ってもらいましょう。
このステップをやるかどうかは各家庭におまかせしますが、やる価値はあるかなと思っています。
家計簿作成を1回経験することで、将来巣立ったときに、家計管理をやるきっかけになるかもしれません。
また小学生で経験しておけば「家計管理はそんなに難しいものじゃない」と思ってくれる可能性もあります。
「ちょっとやってみる?」と聞いてみて興味を持ってくれたら、少しずつ始めてみましょう。
家計管理は絶対役に立つので、興味があるなら、やって損はありません。
ぜひ一度ご検討してみていただければと思います!
まとめ「家族で家計管理に取り組んで、実践的な金融リテラシーを…!」
今回は「家族で家計簿やりませんか??」という提案をさせていただきました!
まとめると、、
- 家族みんなで、家計簿に向き合ってみませんか??
家計のリアルを早めに知っておこう! - 実際に、家計簿を共有している家族はいます!実例紹介はこちら
- 家計簿を手伝ってもらう4つのメリット
- 早い段階で、お金の流れがわかる!
- 家計管理の経験・スキルが身につき、将来の役に立つ!
- 家族みんなで家計を改善することができ、より強固な家計に!
- 親が楽になります。笑
- 子どもが家計簿を手伝うまでの3ステップ
- まずは家計簿をつける!
※すでにつけている人はOK - ある程度まとまったら、家族に共有!
家計簿をみて、お金の会話を増やす! - 興味を持ったら手伝ってもらうのもおすすめ!
- まずは家計簿をつける!
日本は金融教育が遅れているといわれています。
学校での金融教育も増えていますが、学校で知識面を教えることはできても、実践面を補うことは難しいです。



教師が家計簿を見せるわけにはいきませんからね。
となると、こういったリアルを知るのは、家庭教育の役割ということになります。
最初は、少し怖さもあるかもしれません。
でも長期的に考えたら、それ以上のメリットがあると思います。
いつかどうせ知ることなのですから、早めに知ってもらいましょう!
家計簿をもとに、リアルな金融リテラシーを家族みんなでアップさせませんか??



家計簿は「お金」の必須科目!